伝統の三たてに宿る そば職人の技と誇り

そば庄は昭和41年、先代の川原庄太郎が創業、祖父でもある庄太郎は農業を営みながら蕎麦好きが高じ、自らそばを打って食していました。当時二軒あった蕎麦屋が冬季の新そばの季節のみの営業でしたが、「年間食せる蕎麦屋を」と開業いたしました。
- 出石皿そば協同組合 加盟店
- 全国新そば会 加盟店
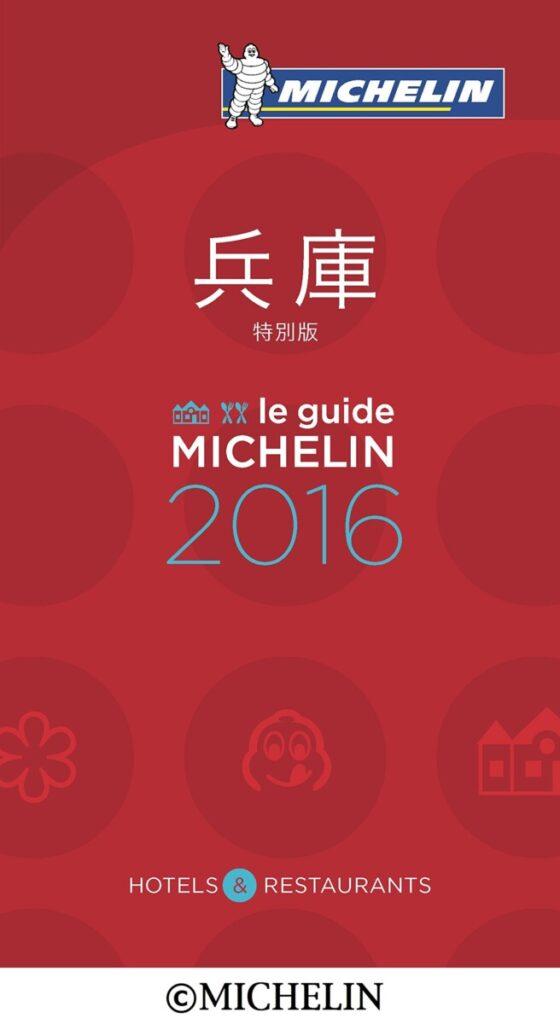
ミシュランガイド2016兵庫特別版
「ビブグルマン」獲得
ビブグルマンとは、3,500円以下でコースや単品料理などの食事が楽しめる、コストパフォーマンスの高いおすすめのレストランです。
取り扱いクレジットカード

出石蕎学館

出石初の本格そば職人育成塾
そば庄では、そば職人を育成する塾を開講しております。
そば職人を目指してみませんか。





